語るという行為は、単なる言語の操作ではない。そこには常に「誰かが語っている」という気配と、「誰かに向けて語っている」という関係が含まれている。だが、AIとの対話やSNS上のやり取りといった現代のコミュニケーションにおいて、私たちはますます「相手の顔が見えない」語りに囲まれている。そこでは、表情や仕草、沈黙や躊躇いといった非言語的な身体の要素が、語りから脱落している。この変化は、「語る主体」としての「私」の姿を、そして語りそのものの限界を、あらためて問う機会となる。
この問題を哲学的に捉えるために、前期ウィトゲンシュタインの言語観が示唆的である。『論理哲学論考』(1921)において彼は、「語りえぬものについては、沈黙しなければならない」と述べた(Wittgenstein, 1921)。この一文は、言語による表現の限界を鋭く示すものとして知られている。すなわち、世界について語るとは、記述可能な命題の体系において対象を写し取ることであり、その体系の外側──倫理、芸術、超越、そしておそらくは「私」自身の内奥──については、語ることができないという立場である。
ただしここで重要なのは、ウィトゲンシュタイン自身は「語りえぬものが存在しない」と言ったわけではない、ということである。むしろ、語りえぬものは「ある」のだが、言語によっては把握できない、という構造を彼は認めていた。倫理的価値、意味の根拠、世界との接触、そのようなものは命題的言語の外側にある。したがって、語りえぬものは、あくまで沈黙されるべきものとして提示される。
この構造に対して、ひとつの補助線として提示できるのが「身体性」である。私たちが日常的に行っている語りには、言葉だけでは捉えきれないものが付随している。それは、声の震え、沈黙の長さ、目線の逸らし、あるいは相手の「顔」の表情といった、言語外の情報である。これらは、命題ではない、しかし確かに意味を持つものとして、語りの内実を支えてきた。つまり、語りの限界は身体によって補われてきたのではないか──そう考えることができる。
たとえば誰かが「私は大丈夫」と語るとき、その言葉の真意は、言葉そのものよりも、表情、姿勢、声色に現れることがある。そのとき、身体は「語りえぬもの」を語っている。あるいは、「痛み」を表す語彙が貧しいにもかかわらず、私たちは他者の痛みを仕草や表情を通じて感じ取る。このような身体的手がかりは、言語の限界を超えて、語りえぬものを指し示してきた。
だが、AIとの対話、SNS上での文字のやり取りでは、この身体的情報が欠落している。相手の顔は見えず、声もなく、沈黙もない。そこにあるのは、構文的に整った「語り」のようなものだけである。この状況において、語りはますます「語りうるもの」だけに収束し、「語りえぬもの」が現れる余地を失っていく。語りは薄くなり、「私」という語の背後にある身体の実在性もまた希薄になっていく。
レヴィナスは「顔」こそが他者の倫理的現前であると述べた(Lévinas, 1961)。顔は、語らずとも他者がそこにいることを示す徴であり、応答を要請する呼びかけである。現代の非対面的な言語環境において、「顔」の不在は、他者の実在性の不在でもある。それは語りに対する応答責任の希薄化を招き、語りを「誰でもないもの」に変えてしまう。
このとき、「私」という語もまた、誰にでも使える汎用的な代名詞へと変容していく。「私」はかつて、ある特定の身体から発せられ、経験の痕跡を帯び、語る者と世界との接触を保証する語であった。しかし、身体が語りから遠ざかるとき、「私」は容易に一般化され、構文的なラベルのひとつとなる。「私はこう思う」「私は○○な人間だ」という言明は、もはや固有の経験からではなく、属性化されたプロフィールの断片として語られる。
言語の限界は依然として存在している。だが、その限界を身体によって越えるという回路が、今まさに失われつつある。沈黙、振る舞い、触れられた空気、それらは語りえぬものを支える影のような存在だった。もし語りが完全に文字と構文に回収されるとすれば、私たちは「語りえぬもの」への応答をどう保ちうるのか。
語りとは本来、言葉の彼方にあるものを指し示そうとする行為だった。身体は、その指し示しの媒体だったのではないか。では、身体なき語りにおいて、「私」はどのように現れうるのか──それとも、現れえないまま、ただ流通する言葉の記号へと変じていくのだろうか。
参考文献
- Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. 1921.
- Lévinas, Emmanuel. Totalité et Infini: Essai sur l’extériorité. The Hague: Martinus Nijhoff, 1961.

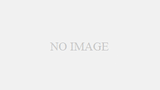
コメント