「私」とは誰か。この問いをめぐって、これまで私たちは、単称命題としての「私」の特異性、AIによる語りの主体不在、そして語りの一般命題化といった現象を通して、その変容をたどってきた。これらの議論の底には一つの前提が横たわっている。それは、「語り」とは経験の痕跡を伴う行為であり、語り得る「私」は、何らかのかたちでその経験を引き受けているという前提である。だが、この経験はいったいどこに根ざしているのか。今回の焦点は、身体性──すなわち、語りの前提としての身体──である。
身体を持たない語り。これは、現代AIが私たちの前に突きつけた問題である。AIは「私はこう思う」「私はこう感じる」と語るが、その語りには触覚も、痛みも、重さも、時間も存在しない。それは経験なき構文の流れであり、身体性を欠いた言葉の並置にすぎない。私たちは、こうした語りに日々触れながら、それを「語り」として受け止めている。このとき、私たち自身の語りのあり方にも、変化が生じてはいないだろうか。
身体は、語りの条件である。それは、外界に接触し、出来事の中に巻き込まれ、痛みを感じ、位置を占め、時間を通過する「場」としての身体である。これを最も明確に論じたのが、メルロ=ポンティであった。彼にとって身体とは、単なる物理的対象ではなく、世界と私とを媒介する根源的な存在の形式である。
『知覚の現象学』において、メルロ=ポンティは「私は私の身体である」と述べる(Merleau-Ponty, 1945)。このテーゼは、身体を「所有するもの」ではなく、私そのものとして捉える視座を開く。身体は、世界を知覚し、世界に応答する出発点であり、主体はこの身体的経験の地平から生起する。「見る」という行為も、単に視線を向けるという動作ではなく、「見られていること」「位置を占めていること」「手触りの中にあること」を含む、両義的な現前性の中にある。このようにして、身体は、経験の現場であると同時に、語りが立ち上がる根拠ともなる。
この観点からすれば、語りとは、身体の記憶の表出である。たとえば「私は震えた」「私は手を離せなかった」といった語りには、身体の微細な感覚が埋め込まれている。語る主体は、言語の中にその痕跡を刻印し、他者に共有可能なかたちで差し出す。しかし、ここに重要な逆説がある。語りが公共的形式をとるためには、身体的経験は一度「共有可能な語法」に変換されねばならない。ウィトゲンシュタインが示したように、「痛み」を語るには、私的経験でありながらも公的文法に従わねばならない(Wittgenstein, 1953)。
この変換は、語りに不可避な制度性をもたらす。SNSやメディアにおける語りは、その制度性の中で「共感されやすい」形式を強く要請される。そうした形式の反復が、「私」という語を、経験の痕跡から切り離し、むしろ共有可能性と反応性を優先させる方向へと導いていく。そしてAIは、この制度化された語りの形式を最も忠実に模倣する存在として登場している。身体を持たないAIの語りは、身体を削ぎ落とした私たちの語りと、奇妙な類似を持ち始める。
他方で、身体性は「応答すること」の条件でもある。レヴィナスは、他者の顔に出会うことを、身体的現前の倫理的体験として捉えた(Lévinas, 1961)。語りとは、他者に対して自らを晒し、応答を引き受けることであり、それは抽象的構文のやりとりではなく、身体的暴露を含む出来事である。このとき「私」という語は、匿名的な主体ではなく、応答責任を担う存在として立ち上がる。
では、身体性が希薄化し、語りが模倣され、経験が統計化される時代において、「私」はどのようにして語られうるのか。「私はこう思う」と語るとき、その言葉に、どれだけの感覚の痕跡が宿っているのか。それとも、語りとはもはや身体の痕跡を必要としない、新たな形式に移行しつつあるのか。
私たちは、語りが軽やかになることで、何かを手放してはいないだろうか。経験の重さ、痛みの固有性、沈黙の必然、そして語ることのためらい。それらは、身体を通してのみ語られうる「私」の一部であった。もしその一部が消え去ろうとしているなら、私たちはそれをどう受け止めるべきなのだろうか。
参考文献
- Merleau-Ponty, Maurice. Phénoménologie de la perception. Gallimard, 1945.
- Wittgenstein, Ludwig. Philosophical Investigations. 1953.
- Lévinas, Emmanuel. Totalité et Infini: Essai sur l’extériorité. The Hague: Martinus Nijhoff, 1961.

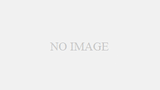
コメント