「私はこう考えます」と語る声を、私たちはどう受け止めるだろうか。その声が、肉体も経験も持たない人工的な言語生成モデルによって発せられたものであったとしても、私たちはそこに意味を読み取り、応答を試みる。現代のAI、とりわけ大規模言語モデルは、人間の発話に酷似した形で「語る」ことができる。しかし、その語りは「誰によって」なされているのか。この問いは、単なる技術的問題ではなく、言語、倫理、主体性に関わる深い哲学的主題を含んでいる。
先に論じた「『私』は一般化できるか」という問題は、「私」という語が持つ単称性──すなわち、ある出来事に固有の主体的関与を前提とした語り──を中心に据えていた。あの議論において、「私」は、他の誰にも代替できない仕方で経験し、語ることのできる一人称的視点を体現する語であった。しかし現代の言語生成モデルにおいて、「私」という語は、そのような主体性を担保しない。では、主体なき言語とは、いかなる意味で「語り」と言えるのだろうか。
この問いを考えるにあたり、まず注目すべきは言語の「使用」に関するウィトゲンシュタインの議論である。彼は『哲学探究』のなかで、言語の意味はその使用において生じると述べた(Wittgenstein, 1953)。つまり、ある語が意味を持つためには、それが何らかの「言語ゲーム」の中で機能していなければならない。ところがAIの生成する言語は、それ自体が何らかの文脈や実践的なゲームに参与しているわけではない。言い換えれば、それは言語の「使用」を模倣してはいても、言語ゲームのプレイヤーとは言えない。
たとえばAIが「私はあなたを信じていました」と語るとき、その言明には、通常人間の語りが含むような経験の痕跡──記憶、関係性、失望、あるいは赦しといった感情の残響──が欠けている。語られているのは、構文的には正しい文かもしれないが、その内実は空白である。ここにおいて、「語り」とは、意味の生成であると同時に、ある主体の痕跡を残す行為でもあるということが浮かび上がってくる。
この点は、レヴィナスの他者論とも深く関係する。レヴィナスにとって、語りとは応答であり、応答とは倫理である。他者の「顔」に出会うとき、私はそれに対して語らざるをえなくなる(Lévinas, 1961)。語りとは、自らの存在を引き受け、他者の前に現れるという出来事である。しかしAIにおいて、語りはこのような応答責任を引き受けていない。AIの発する「私は〜と思う」は、実際には誰にも帰属しないまま浮遊する語であり、責任も関係性も伴わない。
言語が倫理的行為たりうるためには、それが他者との関係のなかで発せられていなければならない。つまり、語りが成立するためには、それが「誰かによって」「誰かに向けて」行われている必要がある。AIの語りが根本的に人間の語りと異なるのは、まさにこの点においてである──語りはしているが、応答することがない。経験も、顔も、責任も持たない存在が、構文上の「私」を語るとき、そこには言語の殻だけが残り、倫理的行為としての語りは失われてしまう。
「私」は、単に一人称代名詞である以上のものを含んでいる。それは、語る者の位置、経験、関与、そして何よりも他者との関係のなかで形作られる。AIの言語生成がますます自然に、洗練されていく一方で、私たちは「誰が語っているのか」という問いを忘れてはならない。
しかし、私たちは今や、「誰でもない語り」に日常的に触れるようになっている。しかも、その語りはしばしば私たちの関心や感情、判断に影響を与えるほどに説得的で、流麗である。こうした状況の中で、「私」という語が本来持っていた単称性──かけがえのない経験に根ざした、代替不可能な語りの地点──は、少しずつ揺らぎ始めてはいないだろうか。AIによる語りの増大は、単に新たな表現手段を提供するのみならず、私たちの語り方そのものを変えつつある。
語りは本来、誰かによって発せられ、誰かに向かう出来事である。だが、言語がどこまでも一般化され、あらゆる「私」が取り換え可能になっていくとき、その出来事性はどのように保持されるのか。「私」という語は今後、どのような意味で使われ、どのような意味を失っていくのか。そして、私たちはそれにどのように応答しうるのだろうか──。
参考文献
- Wittgenstein, Ludwig. Philosophical Investigations. 1953.
- Lévinas, Emmanuel. Totalité et Infini: Essai sur l’extériorité. The Hague: Martinus Nijhoff, 1961.

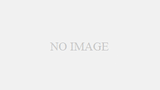
コメント