「顔が見えない語り」「身体を伴わない言葉」といった現代の言語的状況を考える上で、語用論の視点は極めて有効である。語用論とは、言語の意味を単なる構文や語彙の組み合わせとしてではなく、使用される場面──すなわち文脈──との関係の中で捉えようとする言語哲学および言語学の分野である。そこでは、発話者と聞き手の関係、社会的な場面、非言語的な要素(ジェスチャー、視線、間など)が意味の理解にどのような役割を果たすかが問われてきた。
語用論的な考察の基礎を築いたのが、ポール・グライス(Paul Grice)である。彼は1967年の講義「意味」において、言語の意味を「話し手の意図」と「聞き手による意図の認識」によって定義した。つまり、ある言葉が意味を持つのは、それが文脈の中でどのような意図を伝えるかによって決まる。彼の提唱した「協調の原理(Cooperative Principle)」とそれに伴う「会話の含意(conversational implicature)」は、意味がしばしば語られたものそのものではなく、「語られなかったが理解されたこと」に宿るという事実を示している(Grice, 1975)。
たとえば、「寒くない?」という問いが、単なる天候の確認ではなく、「窓を閉めてほしい」という要望として機能することがある。ここには、言葉の意味が身体的・環境的な状況と深く結びついていることが表れている。聞き手がその意図を正確に理解するには、場の空気、話者の声の調子、表情、目配せといった非言語的要素が重要になる。すなわち、言葉の意味は常に身体とともにある。
この議論をさらに洗練させたのが、ダン・スパーバーとデードラ・ウィルソンによる「関連性理論(Relevance Theory)」である。彼らは、理解とは単なる情報の受け取りではなく、「話し手の意図に対して最も関連性の高い解釈を選び取る認知的行為」であると述べた(Sperber & Wilson, 1986)。この理論においても、非言語的手がかりや身体性は、解釈の可能性を方向づける重要な要素とされる。語りの意味は、それが発せられる場面に依存しており、解釈の行為には身体を含んだ「場面の知覚」が不可欠なのである。
こうした伝統を踏まえ、現代日本において語用論の理論と実践を架橋している研究者の一人が三木那由他である。三木は、意味とは「人と人との間で行われる活動の中で立ち現れるものである」と強調し、言葉の意味が常に「行為」として把握されるべきであることを説く(Miki, 2021)。ここでの行為とは、身体を通じて現れる振る舞いや、場に応じた応答性を含んでいる。言葉は孤立した情報ではなく、「応答的な身体によって支えられた出来事」として意味を持つ。
このような語用論的視点を採り入れることで、前稿「顔のない語り」で述べたような、AIやSNSにおける非身体的な語りの問題は、より理論的に補強される。言葉が意味を持つためには、それが使用される文脈のなかに身体性が含まれていなければならない。言い換えれば、語りの理解には常に「そこにいる身体」が不可欠である。
現代の言語生成AIは、統計的に最適化された応答を返すことができるが、それが語用論的文脈をどこまで理解しているのかは依然として疑問が残る。たとえば「怒ってないよ」という発話が、実際には怒っていることを意味するためには、声色や表情といった身体的手がかりが不可欠である。このとき、AIが語る言葉には「ズレ」が生じる。それは、文脈のなかにいる身体の不在という根源的な限界に起因している。
語用論は、言語の理解がいかに身体や場との関係性に依存しているかを明らかにしてきた。この視点から見ると、「語りの限界は身体によって乗り越えられてきた」という補助線は、単なる直観ではなく、理論的にも支えられた立場となる。語りの理解とは、常に「誰が」「どこで」「どういうふるまいの中で」語ったかを引き受ける営みである。
そして「私」という語が意味を持つためにも、その語が発せられる身体が不可欠なのだ。AIが「私」を語るとき、その語は依然として文脈の空白のなかに浮遊している。それを語りと呼ぶべきかどうか──この問いは、言葉が身体とともにあることを前提とする語用論の視座から、あらためて深く問い直されるべきものである。
参考文献
- Grice, Paul. “Logic and Conversation.” In Syntax and Semantics Vol. 3, eds. Cole and Morgan, 1975.
- Sperber, Dan & Wilson, Deirdre. Relevance: Communication and Cognition. Harvard University Press, 1986.
- 三木那由他『意味のしくみ』ちくま新書、2021年。

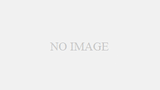
コメント