私たちはしばしば、一般論に安心感を覚える。
──「人間関係は○○が大切」「Z世代は××の傾向がある」「○○型の人は△△しがち」。
SNSのタイムラインにも、書店の棚にも、日常会話の合間にも、そうした「○○は△△である」といった語りが満ちている。こうした一般論的語りはある種の「わかりやすさ」を我々にもたらしてくれる。特段深く考える必要もなく、ただ文面をそのままなぞるだけで何かを知ったような気になれる。こうした一般論的語りが孕む「わかりやすさ」の魅力に我々はなかなか抗えない。
こうした「わかりやすさ」は他者や外的な事象のみでなく、しばしば自分自身をも対象とする。 「自分はこういうタイプの人間だ」「こういう傾向がある」と一般論的な定義に自身を当てはめることにより、自分という人間に対する不可解さや不安定さを解消しようとする。このようにして「自分自身を一般化する」ことで、我々は自身の居場所を定めることができ、「わかった気になる」ことで、安心感や帰属意識といった快楽を得ていると考えられる。
つまり、巷間に流布する一般論に自分を当てはめることで、私たちは納得して安心できるのだ。「私はこういうタイプの人間なのだ」と。そしてこの納得はしばしば私たちの日々の振る舞いにも影響を与えていくことになる。
だが、ここで考えてみてほしい。この納得感は果たして正しいのだろうか?この一般論は他人によって設計された“わかりやすい物語”の中に、自分を置いてしまっているだけではないだろうか。
20年以上前に人気を博した『ファイナルファンタジーX』というゲームの中で、冒頭大きな事件に巻き込まれ右往左往する主人公に対し、あるキャラクターが次のようなセリフを投げかける。「覚悟を決めろ。これはお前の物語だ。」この言葉は、劇中に登場する主人公に向けられている一方で、プレイヤーに対しても、ただ「与えられた物語をなぞる」のではなく、「あなただけの物語を生きる」ことを促すような力を持っていた。
この力強い言葉に比べて、現代において私たちが出会う物語は、あまりに親切で、あまりに予定調和だ。なんの犠牲も覚悟もなく受け入れられ、ただ消費され消化されるだけの空虚な物語。果たして、そのような物語に自身を位置付け、規定するのは正しい行いなのだろうか。
ダニエル・カーネマンに代表される行動経済学のこれまでの研究で、我々は様々な認知バイアス1──代表性ヒューリスティックや確証バイアスなど──を有していることが明らかになっている。我々のこうした傾向性ーーすなわち「自分に当てはまりそうな語り」を過剰に信頼し、その情報に合致するものばかりを集めようとする傾向性ーーもまた、こうした認知バイアスによって説明されうるものだろう。これは判断の効率性を高める一方で、思考の多様性や逸脱を削ぎ落とす、すなわち私たちが本来的に有している個性や特性を、分かりやすい言葉の裏側に押し込んでしまうのだ。
私たちは、「一般論の中の自分」というフィクションを愛しているのかもしれない。
そして、そのフィクションのなかで、安定と所属の感覚を確保しようとする。
だが同時に、「そのように語れない自分」──例外的で、ノイズのように現れる自分──をどこかで持て余してもいる。
インターネットの勃興とSNSの普及という情報革命を経た現代社会では、多様な情報を瞬時かつ膨大に得られるようになった半面、「自分の言葉」を見つけることが非常に難しくなっている。このブログでは、そうした「自分の言葉で語る」ことの重要性を、様々な観点から考えていきたいと思う。
私たちは、理解されることを望んでいるのだろうか。
それとも、あらかじめ用意された物語のなかに、居場所を見つけたふりをしているだけなのだろうか。
- Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011). ↩︎

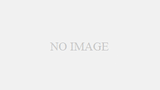
コメント