なぜ「信じる力」が問われるのか ─ 情報“氾濫”社会と正しい判断について
“We are such stuff as dreams are made on.”
— William Shakespeare, The Tempest, Act IV, Scene 1
「これは本当のことだと思う」
「この人は信用できる」
「そんなの信じられない」
こうした「正しさ」に関する判断を、私たちは日常生活の中で何度も下しています。ニュースやSNSの投稿、誰かの体験談、YouTubeの解説動画など──現代社会にはさまざまな情報がまさに洪水のように溢れており、それらに接するたびに、私たちは「信じる/信じない」を瞬時に判断しています。そしてそうした判断は、私たちの日々の思考や行動の基盤となっています。
しかし、そのようにして私たちが行っている「信じる/信じない」の判断は、果たして信頼できるのでしょうか。
現代社会は、情報が過剰にあふれ、かつてよりも遥かに複雑化した時代です。私たちは日々、無数の情報にさらされながら、「何を信じるべきか」「どれが正しそうか」を、意識的であれ無意識的であれ、瞬時に選び取らなければなりません。一方で、SNSや動画サイトなどでは、もっともらしく見えるが真偽の疑わしい情報や、個人の感情や偏見に基づいた言説が拡散し、それが多くの人に“正しいもの”として受け入れられてしまうケースも少なくありません。
また近年では、「統計」「データ」「確率」といった言葉が、しばしば客観的で中立的な真理の代名詞として扱われています。グラフや数値が添えられるだけで、内容が信頼できるような印象を与える──そんな場面は少なくありません。しかし、こうした確率や統計に基づく言説をどこまで信じてよいか判断するためには、一定の知識や理解が求められます。そもそもそうした言説が私たちにとってどのような「情報」なのか──それは「知識」と呼べるのか、それとも高度に形式化された「信念」「予測」「期待」に過ぎないのか──といった問いは、哲学的にも極めて奥行きのあるテーマです。
信じるとは何か。知るとはどう違うのか。
なぜ私たちはある情報を信じたくなるのか。
そして、私たちはどのようにして「信じるに値する言葉」や「意味のあるデータ」を選び取ることができるのか──。
このブログでは、そうした問いにじっくりと向き合っていきます。「正しさ」「知識」「信頼性」「語り(騙り)」「検証」「確率」「統計」などをキーワードに、情報社会に生きる私たちが、自分自身の「信じる」という行為を改めて見直すための、思考の道具を模索していきます。
知識や正しさとは、単なる事実の積み重ねではなく、「誰が、どのように語り、それが誰に、どう届いたのか」という文脈と関係性の中で形成されるものです。ゆえに、科学的・数学的な言説のように、時間や空間に対して普遍的に通用する真理というものは、実のところほとんど存在しない──その事実に、まずは真正面から向き合わねばなりません。
このブログは、情報リテラシーに関するノウハウや技術の解説を目的とするものではありません。読者の皆さんが、自分自身の「信じる」という行為に対して、より丁寧に、より深く向き合えるようになるための“道具立て”を提供する場でありたいと考えています。
そのため、このブログは明確な「正解」にたどり着くことを目的とはしていません。むしろ、簡単には答えの出ない問いを持ち続けること──持ち続けようとすること──その営みそのものを、大切にしていきたいと思っています。
もしあなたが、日々の情報に触れる中で「これって信じても大丈夫?」と感じたことがあるのなら、このブログから、何かしらのヒントを得られるかもしれません。
情報が氾濫するこの時代において、判断に迷ったときの小さな道しるべとなれれば幸いです。

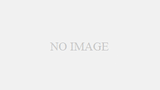
コメント