「『私』について語る」とは、いかなる行為なのか。この問いは、一見自明に思えるが、言語哲学と心の哲学の交差点において極めて深遠な問題を孕んでいる。私たちは日常的に、「私はこう感じた」「私はそれを見た」「私はあの人を信じていた」といった言明を発する。これらは、文法的には「人間とは〜である」や「私たちは〜しがちである」といった一般命題と同様の構造を持つが、そこに含まれる「私」という語は、単なる文法的主語にとどまらない、より根源的な指示性を帯びているように思われる。
この「私」という語の哲学的特性を分析するための鍵概念が、「単称命題(singular proposition)」である。単称命題とは、特定の個物を直接的に指示する命題のことであり、固有名や指示詞を含む命題、たとえば「この人は〜である」「あの山は〜である」などが典型例である。これに対して、一般命題はある性質が不特定多数の対象に当てはまることを述べる。
単称命題の理論的基礎を築いたのは、Gottlob FregeとBertrand Russellである。Fregeは「意味(Sinn)」と「意義(Bedeutung)」の区別を導入し、言語表現がいかにして指示対象と結びつくかを分析した(Frege, 1892)。たとえば「明けの明星」と「宵の明星」は異なる意味(Sinn)を持つが、同一の意義(Bedeutung)、すなわち金星を指す。この区別は、同一対象への異なる認知的態度の可能性を認めるものであり、思考の内容と外部対象との関係に対して繊細な理論枠組みを与えた。
これに対してRussellは、「記述理論(theory of descriptions)」において、表面的に固有名に見える表現も実は隠れた記述であると分析し、命題の意味はその構成要素が具体的に対象を指示することで成立するとした(Russell, 1905)。彼の「ラッセルの原理」によれば、命題の構成要素が実際に指示対象を持たなければ、その命題は意味をなさない。たとえば「現在のフランス国王は禿げている」という命題は、一見意味を持つようであるが、実在するフランス国王がいない以上、指示に失敗しており、命題全体が意味を失っているということになる。
このような古典的議論を踏まえつつ、現代的な観点から命題と思考の関係を再構成したのがArthur Sullivanである。Sullivanは、「単称命題(linguistic structure)」と「単称思想(cognitive act)」を区別し、言語と思想の関係をより明示的に捉えた(Sullivan, 1998)。彼によれば、単称命題とは言語によって表現された意味構造であり、単称思想とはある個物を直接的に思考において捉える行為である。この区別により、言語表現としては同一の命題が、思考のレベルでは異なる仕方で把握されうることが明らかになる。
たとえば「私はあなたを信じていた」という言明において、「あなた」が指す相手は、言語的には指示詞によって明示されているように見えるが、その語りが成立する背景には、話者にとっての関係性、経験、感情といった非言語的要素が深く関与している。すなわち、単称思想とは、言葉によって十全に表現されえない、固有の経験への接触の痕跡である。
このような文脈において、自己言及的な表現、すなわち「私は今ここにいる」「私はこれを見ている」といった発話が持つ特殊な意味論的構造に注目したのがJohn Perryである。彼はこのような発話が、単なる命題内容としてではなく、話者の文脈的立場(indexicality)によって意味を持つと主張した(Perry, 1986)。これにより、「私」という語は、常にその場の話者を指示するという動的・文脈依存的な性質を帯びることが示される。
David Kaplanはこの文脈依存性を「直接指示理論(direct reference theory)」として体系化し、語の意味を「character(語の一般的用法)」と「content(特定文脈での意味)」に分けることで、文脈的要素を明示的に取り込むモデルを提示した(Kaplan, 1989)。
さらにScott Soamesは、命題の意味を語の使用における行為や意図に結びつける方向で理論を展開し、意味とは単なる文の構造に還元されるものではなく、使用の場における行為的側面に依存することを強調する(Soames, 2005)。このような視点は、「私を語る」という行為が、単なる文の産出ではなく、出来事的・行為的な意味生成のプロセスであることを浮かび上がらせる。
ここで問題となるのは、「私」を語るという行為が、どのようにして単なる自己記述を超えて、不可代替的な主体性の表現となりうるかという点である。たとえば、「私は内向的な性格です」といった言明は、自己をあるカテゴリーに位置づける試みに他ならないが、それは一般的性質の言明としての性格を持つゆえに、「私」の特異性を語っているとは限らない。むしろ、そうした言明において「私」は、あらかじめ与えられた枠組みに還元され、単称性の力を失ってしまう可能性がある。
対照的に、「私」という語が本来担っているのは、その語を発する者自身にしか引き受け得ない出来事、代替不可能な経験の痕跡であり、それゆえにこそ単称命題的性格を持つ。単称思想の観点から見るならば、そこには単なる認識の記述を超えて、「誰が」それを経験したのかという主体の介在が要請される。
このような観点は、他者との相互理解の問題とも密接に関わってくる。単称命題が成立するためには、聴き手が話者の意図する指示対象を同定できる必要がある。しかし、単称思想としての「私」の経験は、常に他者には把握しきれない余白を伴う。このズレこそが、哲学的自己言及の核心であり、「私を語る」営みが単なる情報伝達にとどまらない、存在論的・倫理的な意味を持つ理由である。
「『私』は一般化できるか」という問いは、単なる語用論的な問題ではない。それは、言語において個としての経験をいかに語りうるか、語ることがいかなる限界と可能性を持つのかを問う、深遠な哲学的主題である。そしてその問いへの応答は、私たちがどのような語り方を選び、どのような沈黙を選ぶかにかかっている。「他でもない私の物語」として語られる「私」の言葉は、普遍的な意味を帯びると同時に、常に特定の一者から発せられる固有の響きを持っている。
参考文献
- Frege, Gottlob. “On Sense and Reference” (1892). In Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege, Blackwell.
- Russell, Bertrand. “On Denoting” (1905); also see Principia Mathematica (1910).
- Sullivan, Arthur. “Singular Propositions and Singular Thoughts.” Notre Dame Journal of Formal Logic, 39(1), 1998.
- Perry, John. The Problem of the Essential Indexical. Center for the Study of Language and Information, 1986.
- Kaplan, David. “Demonstratives,” in Themes from Kaplan, eds. Almog, Perry, Wettstein. Oxford University Press, 1989.
- Soames, Scott. Reference and Description: The Case Against Two-Dimensionalism. Princeton University Press, 2005.

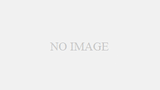
コメント