かつて「私」という語は、ある特定の出来事のなかで、他の誰にも代替されない立場から語られるものであった。その語りは、経験の痕跡を帯び、判断の責任を引き受け、語り手の倫理的姿勢を含んでいた。しかし今、この「私」という語は、かつてのような単称性──ある唯一の個を直接に指示する力──を徐々に失いつつあるように見える。現代の情報環境において、「私」という語はしばしば属性、傾向、カテゴリーの記号として語られる。内向的な私、論理的な私、共感的な私──そこには、固有の出来事に深く関与する「私」ではなく、あらかじめ定型化された「誰か」がいる。
この現象は、「『私』は一般化できるか」という初回の論考で提示した問題系と直結している。あの議論では、固有名や指示詞を含む単称命題が、特定の対象に対する直接的な言及を本質としていることを確認した。とりわけ、「私」という語は、その発話者にのみ使用を許された語であり、文脈依存性(indexicality)を強く帯びた特異な言語的現象であった。だが、AIによる語りの台頭により、「私」という語が誰にでも使われうる、極端には主体なき語りにも用いられるものとして拡張されつつある。このとき「私」という語は、もはや単称性を担保するものではなく、一般命題的な性格を帯び始める。
ここで思い起こされるのは、マクダウェルが述べた「経験とは概念の中に開かれたもの」であるというテーゼである。語りとは、世界との接触を経た判断の形式であり、単なる情報の記述ではない(McDowell, 1994)。したがって、「私」という語が意味を持つのは、それが経験に裏打ちされているときである。しかし、語りの形式がAIによって模倣され、言語があらかじめ構文的・統計的に予測可能なものとして生成されるようになると、「私」はその経験性から切り離され、一般的なパターンの中に埋没していく。
一方で、デネットの議論が示唆するように、「語りが自己を構成する」という視点に立てば、一般命題化された「私」もまた、語りうる形式の一つとして肯定されることになる(Dennett, 1991)。むしろ語りの中に安定した構文と様式が確保されている限り、それは社会的に通用する「私」としての機能を果たす。ここでは、「私」とは経験の痕跡というよりも、他者とのやりとりの中で生成され、理解される記号的役割を担う存在である。
このような対比を踏まえると、現代における「私」という語の変容は、経験の固有性から意味の可搬性への移行として理解できる。語りが「誰か」のものでなくとも意味を持つようになるとき、「私」という語もまた、属性の一つとして運用されるようになる。たとえばSNS上でのプロフィール文や投稿文において、「私は○○なタイプです」「私は共感力が高い人間です」といった言明は、「私」の特異性を示すのではなく、特定の属性の表明として機能している。
この現象は、AIによる語りの模倣によって引き起こされたものというより、むしろそれを可能にした土壌──あらゆる語りが共有可能であるべきだという現代的な志向性──と共振しているのではないか。常に誰かとつながっているという感覚、他者に理解されることを前提とした自己表現、それらは「私」の語りを、あらかじめ共有されうる一般的構文へと変容させていく。
このとき、「私」という語が担っていた単称性──他者にとって常に理解不可能な余白を含んだ語りの地点──は、徐々に意味を失っていく。語りの中で「私」が他者との共通理解を前提としすぎるとき、「私」はもはや、かけがえのない誰かとして語るのではなく、「誰にでもなりうる誰か」として語られてしまう。
では、現代において「私」という語は、どこへ向かっているのだろうか。語りの一般命題化は、語りの倫理性──つまり「私が語る」ことの責任や出来事性──をどのように変容させていくのか。あるいは、「私」があくまで誰かに応答する存在であるならば、その応答関係の形式自体が変わりつつあるのではないか。
この問いは、次なる論点──「身体性と『私』意識の関係」へと開かれている。すなわち、語りが経験と結びついていたとき、それは身体を通じてなされた。だが、身体が希薄化し、語りが軽やかに模倣される時代において、なお「私」とは誰なのか。この問いを引き継ぎながら、考察を続けていきたい。
参考文献
- McDowell, John. Mind and World. Harvard University Press, 1994.
- Dennett, Daniel C. Consciousness Explained. Little, Brown and Co., 1991.

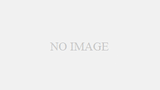
コメント